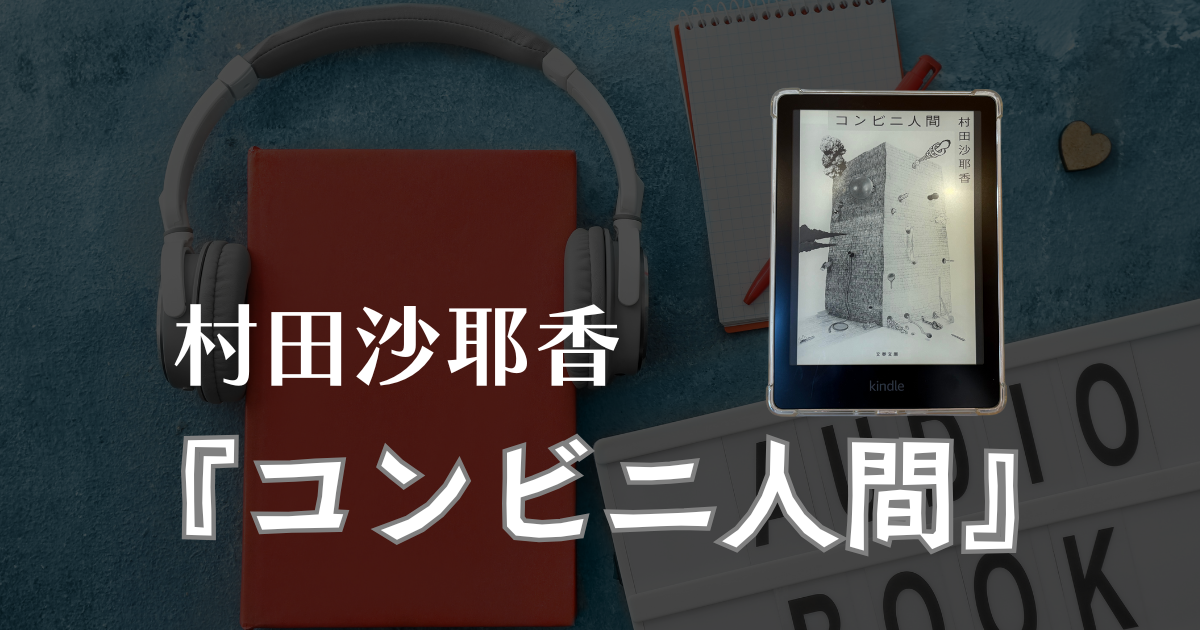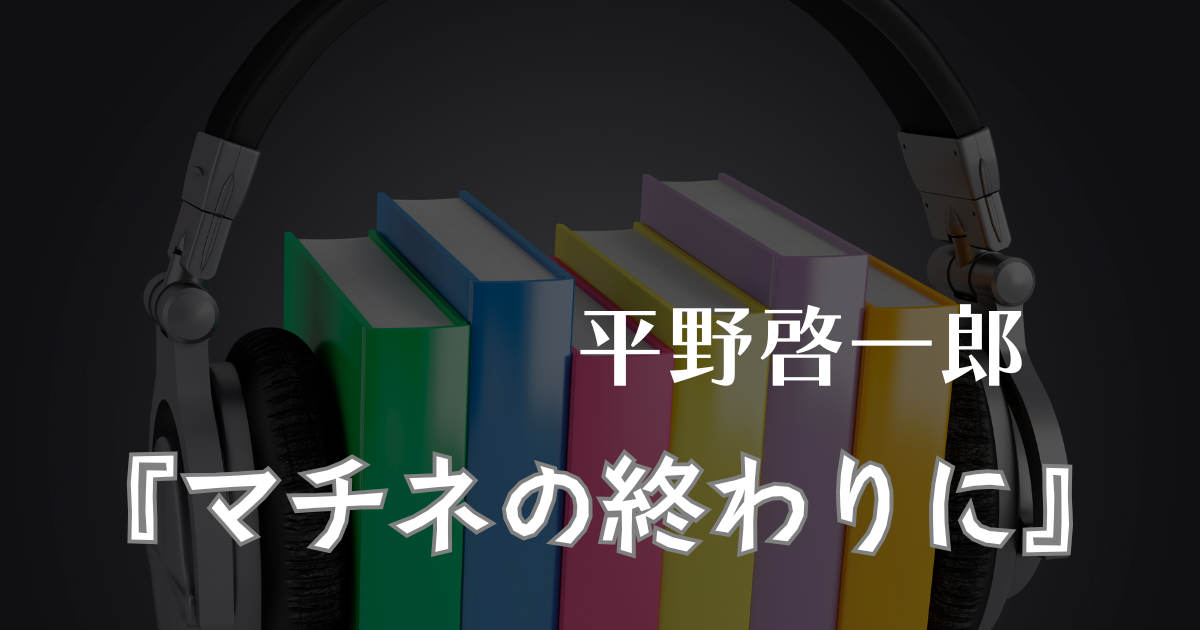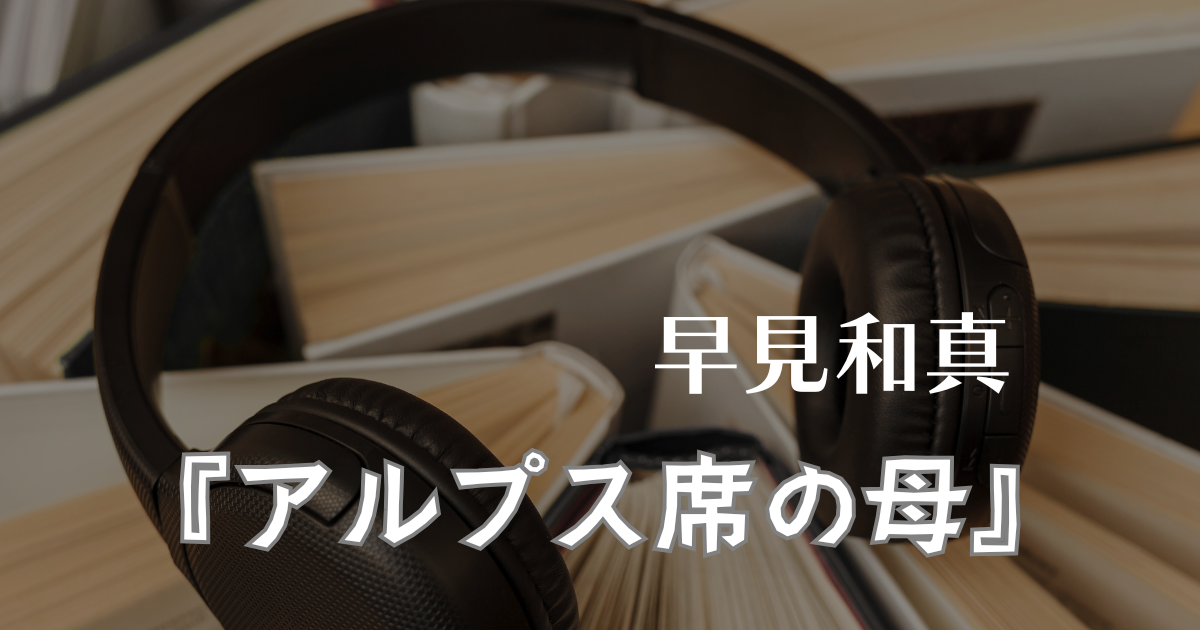コンビニエンスストアは、音で満ちている。
から始まるこの書籍は、始終、聴覚を刺激される書籍である。
コンビニのなかで決して止むことのない繊細な音の描写は、私の想像を掻き立てた。
また、Audible版では大久保佳代子さんの朗読が、無機質な雰囲気にとてもマッチしている。
そして、この書籍の描写の繊細さは、聴覚を刺激するだけではない。
『人間の“普通”とはなにか?』 と、問われまくるのである。
マイノリティの側に立ってみて初めて見える景色が、この書籍のなかにはたっぷりと詰まっていた。
私はストーリーを深く理解したい衝動に駆られ、結局、Kindle版もダウンロードした。
というわけで、今回は『コンビニ人間』について、読書感想を書いてみることにする。
『コンビニ人間』を手に取った理由
私は本が好きだが、胸を張って「読書が大好きです」と言えるほどでもないし、難しいことはなにも知らない。
それを裏付ける事実として、この書籍が芥川賞受賞作品であることを知ったのは、読了後のことだった。
そんな私がこの本を手に取った主な理由は、以下の2点である。
- 謎多きカバー
- 多くの人に読まれているらしい
あとは、“なんとな~く呼ばれるように”という感覚的なところも非常に大きかったように思う。
『コンビニ人間』のカバーは、金氏徹平氏の作品
我が家の10代の娘ふたりも、「これは何の絵?」と言いながら強い関心を示した。
“なんだろね~”と言うしかなかったのだが、artfrontgalleryに掲載されている金氏徹平氏のところを訪れてみたら、“なるほど”と思ったのであった。
サイトにはこのように書かれていた。
現代社会で再生産され続ける情報のイメージを、リズミカルに反復と増幅を繰り返し展開させることで注目を集める。
artfrontgalleryより
金氏徹平氏のサイトを訪れたことで、『コンビニ人間』のカバーデザインが理解できたわけではないのだが、妙に納得してしまい、勝手にスッキリした。
そして、人目を惹くこのデザインは、本の内容を裏切ることなく本の顔を飾っているなぁというのは、素人の偉そうな感想である。
こちら側の常識を疑わないからこそ、あちら側に対する『Why?』は無遠慮に振る舞われる
こちらの書籍の主人公は、36歳未婚女性、古倉恵子。
恵子は大学卒業後も就職はせず、18年間もの間、同じコンビニでバイトをし続けている。
まず、この一文だけ読んだ人は、恵子に対してどのような印象をもつだろうか。身近に恵子のような人がいたら、どのように思うだろうか。
これは私の勝手な憶測だが、
- なにか事情があるのかな?
- なんで就職しなかったのかな?
- なんでずっと同じコンビニ?”
など、いろいろな『Why?』が浮かぶのではないだろうか。
相手に対して抱く「なぜ?」は、多くの場合、こちら側(マジョリティ)にとっての常識とのズレから浮かぶことが多いと思う。
つまり、マイノリティの側に立つと、「なんで?」の質問攻めに遭う機会が増えるということだ。
実際のところ、私自身がそうだった。
自閉症スペクトラム&不登校姉妹の母として実感してきた、他人からの無遠慮な「Why?」
人は悪気なく、私にいろいろ聞いてくれる。
- 「なんで娘ちゃんたちは学校に行けなくなっちゃったの?」
- 「なんで娘ちゃんたちはマスクを着けないの?」
- 「なんで娘ちゃんはいつも草履を履いているの?」
- 「なんで娘ちゃんたちは昼間にお母さんと一緒にお買い物してるの?」
という感じで、挙げだしたらキリがない。
Why?のシャワーを浴び続けた結果、私はこう思うようになった。
人が「なんで?」と相手に聞くときは、自分の常識を疑っていないときなのだ、と。
しかし、無遠慮に向けられる「Why?」は、こちら側としてはとても疲弊する。
アナタにとって私たち親子の日常は異常に見えるかもしれないが、私たち親子にとっては、通常の当たり前なのだから。
マジョリティの人たちが携えた常識とマイノリティ
世のマジョリティたちは、自分たちの常識が世界の中心にあるのかもしれない。
もしかすると、常識が、というよりも、常識を携えた自分たちが、と言い直したほうが正しいかもしれない。
世界の中心から離れれば離れるほど、いわゆる常識は薄れ、やがてはかけ離れたものになる。
自分たちが世界のどの辺りに位置しているのか?なんて、無意識だとは思うが、おそらく世界の中心付近に存在しているのが安心なのだろう。
だから当然、世界の中心よりも遠く離れている人たちは好奇の目で見られる。
なぜ?と。
だからと言って、放っておいてくれるわけでもないのだ。
ここで、やや過激な白羽さんのセリフを引用してみようと思う。
「皆が足並みを揃えていないと駄目なんだ。何で三十代半ばなのにパイトなのか。何で一回も恋愛をしたことがないのか。性行為の経験の有無まで平然と聞いてくる。『ああ、風俗は数に入れないでくださいね』なんてことまで、笑いながら言うんだ、あいつらは!誰にも迷惑をかけていないのに、ただ、少数派というだけで、皆が僕の人生を簡単に強姦する」
『コンビニ人間』より
やはり、白羽さんの発言は過激ではあるが、私には共感できる部分があった。
皆さまはいかがだろうか。
どこからどこまでが“生き物”なのか、という倫理観を突きつけられる
恵子がまだ幼稚園児の頃、公園で小鳥が死んでいたというシーンがある。
死んだ小鳥を掌に乗せ、母のもとに行った恵子は「これ、食べよう」と言う。
「え?」という母に対し、「お父さん、焼き鳥好きだから、今日、これを焼いて食べよう」と続けるのだ。
この後の、恵子から見える描写がとても斬新で興味深い。
皆口を揃えて小鳥がかわいそうだと言いながら、泣きじゃくってその辺の花の茎を引きちぎって殺している。
『コンビニ人間』より
小鳥は、「立入禁止」と書かれた柵の中に穴を掘って埋められ、誰かがゴミ箱から拾ってきたアイスの棒が土の上に刺されて、花の死体が大量に供えられた。「ほら、ね、恵子、悲しいね、かわいそうだね」と母は何度も言い聞かせるように囁いただ、私は少しもそうは思わなかった。
『コンビニ人間』より
大人が考える“異常”は本当に異常なのか?
私はかつて幼稚園で働いていたことがある。
その頃からずっと考える機会があるたびに考えてきたことが、このような倫理観であった。
おそらく、正解はないのだろう。
これもまた、多くの人がどのように考えるか?が重要であり、それがあたかも正解となりやすい問題なのだと思う。
たしかに、公園で死んでいた鳥を掌に乗せて、これを「食べよう」という発想に至る子どもは少ないはずだ、現代の日本においては。
でも、もし大飢饉が訪れたら・・・?
恵子の発想は、とかく異常ではなくなるかもしれない。
というよりも、多くの人の目に、“異常”とは映らなくなる、と言ったほうが良いかもしれない。
それから、『花を殺す』という見方をする人も、おそらく少数派ではあると思うが、それはなぜだろう。
花も“生きている”ことに違いないのに、「花を殺す」とは言わない。
これは動物と植物の違いなのだろうか?
しかし、花を乱暴に引きちぎったりする子どもを見て、「お花さんがかわいそうだよ」と注意するおとなもいる。
このように考えてみると、これはある程度、独断と偏見にに委ねられるのかもしれない・・・。
なぜなら、「お花さんがかわいそうだよ」と注意するおとなが、ゴキブリや蚊に対し、「かわいそうだから」と言って優しく捕まえて外に逃がしてやれるとは、あまり考えられないからである。※なかには、そうできる優しい人がいることも知っている。
これもまた、多くの人が“フツー”と感じる感覚を持っているか否かで、正常か異常かが分かれてしまう部分なのかもしれない。
【まとめ】村田沙耶香さんのコンビニ人間は咀嚼しがいのある一冊!
村田沙耶香さんの『コンビニ人間』は、とても読み応えのある、また、咀嚼しがいのある一冊でした。
Audible版では、大久保佳代子さんの朗読が書籍の内容とマッチしていて秀逸なので、読書が苦手なかたでもお楽しみいただけるかもしれません。
物語の終盤では、主人公の恵子は自身がコンビニ店員という動物なのだと気付き、白羽さんに訴えるシーンがあります。
ここで、人間という生き物とは?と考えさせられます。
そして、どのような人が“まっとうな人間”なのか、と。
独特な価値観をもった人は、人間から逸脱していると認定され、他者から排除されるのが運命なのでしょうか。
マイノリティでもあり、マジョリティでもある私にとっては、正直よくわかりません。
どちらの立場も日々経験しているからこそ共感できる部分も多くあったのかもしれない、というのが最後の感想です。
皆さまはいかがでしょうか。

もりー
というわけで、最後までお読みくださりありがとうございました。