私の娘はふたりとも、ASDで境界知能である。
ふたりはやがて学校にも行けなくなり、いわゆる『不登校』という道を歩み、早5年が経過した。(時期の差はあります)
母親である私は、様々な現実を受け入れるたびに『怒り』や『悲しみ』と向き合ってきた。
障害受容も言うほど簡単なことではなく、自分は受け入れたつもりでも世間の反応は様々で、反応を受けるたびに落ち込んだりもしたものだ。
と、つい最近まで、こんな感じだった私。
しかし、自分の中に小さな違和感があることに気づきはじめていた。
それが、ジェーン・スーさんの書籍『ひとまず上出来』の中の言葉により、決定的となったのだった。
というわけで、今回は最近の私の心境の変化について書いてみようと思う。
負け犬の遠吠えと被害者ヅラは相性が良い
私はいつからか、『現代の学校教育について思うこと』や『差別や偏見について』など、あふれる思いを発信するようになっていた。
発信媒体は、実に様々である。
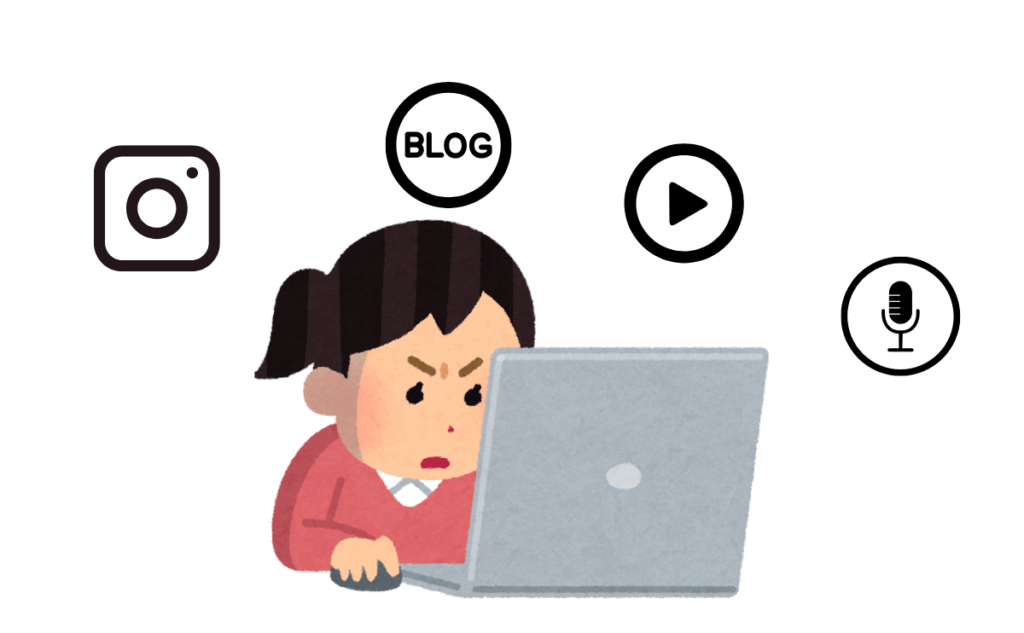
今思えばであるが、その原動力の80%は怒りや悲しみ、残りの15%は承認欲求、残りの5%は同じような境遇の方々と出会いたいという願いだったような気がする・・・。
そして最近、自分の発信に対し、小さな違和感を感じるようになっていた。
具体的には、
という感覚である。

そのように感じた理由を分析してみた結果は、以下の通りである。
おそらくではあるが、
- もっと学校教育が◯◯だったら
- もっと支援が◯◯だったら
- もっと世間が◯◯だったら
と、自分にとって枯渇している部分ばかりに目を向け、叫んでいたからだと思う。
まさに、「被害者ヅラをしていた」ことを認めるしかない感じだ。
自己正当化をするつもりはないが、声を上げることの重要性も無視はできないことだけは書いておきたい。
しかし、よほどの影響力をもつ人間でない限り、当事者から見えている景色をどんなに声高に叫んだところで、そう遠くまでは届かない。
届く範囲は、同じような境遇の人たちや、このような分野に興味のある人たちくらいまで、という感覚だ。
この感覚がより、『負け犬の遠吠え感』をより助長させるのかもしれない。
ここで念の為、誤解を防ぐべく、防御線を張っておくことにします。
私はこれまで書いたような行為を否定するつもりはまったくありません。
むしろ必要な場合もあると考えています。
なぜなら、同じような境遇の方たちに届け、届けられ、一時的に救われることもあるからです。
傷ついている自分を手放さずに年を重ねた成れの果ては・・・(想像)
散々叫びちらしておいて、「どの口が言ってんだよ?!」という感じではあるのだが、最近気がついてしまったのだ。
これについてもう少し噛み砕いてみると、
想像してみると、これってとっても怖いこと。

復讐心に燃えるおばあちゃんになってしまいそう・・・。
しかも私は、「少しでも誰かのお役に立てたら」という大義名分を掲げていたので、とてもとても厄介だと思う。※この思いに嘘はありませんが。
だって、大義名分がさらに、私の隠れ蓑になっていたのだから。
スーさんの書籍にはこう書かれている。
自分で自分を被害者ポジションに拘留すると、ささくれを剥かれるような不愉快な痛みと、ぬるま湯に浸かっているような居心地の良さの両方が同時にもたらされたことを思い出します。
このワンフレーズと出会ったとき、私は雷に打たれたような衝撃を受けた。
なぜなら、まさに私自身がそうだったからである。
さきほどのフレーズには、このような続きがある。
あれ、不思議ですね。最初は心の底から傷ついていたはずなのに、一日もこんな自分とはオサラバしたいはずなのに、だんだんと「傷ついている自分」を手放せなくなっていく。
そうなんですよ。
人にはタイミングというものがあるから、私にとってもアナタにとっても“手放すのに丁度よい時期”があるというのは、自身の考え方の根本にある。
しかし問題は、
放っておいたら“手放すのに丁度よい時期”は、いつになっても訪れない
ということなのだ。
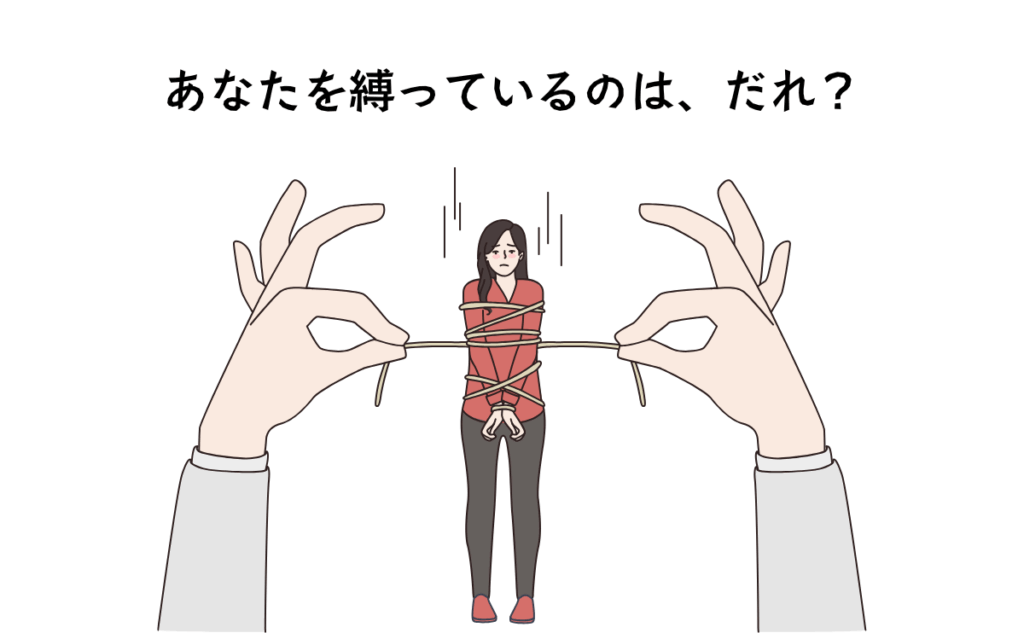
ジェーン・スーさんの一言で、半覚醒状態だった私の目が醒めた
先程の引用文はさらに続き、このようなトドメが刺されている。
正しい弔いが終わっていないからなんでしょう。
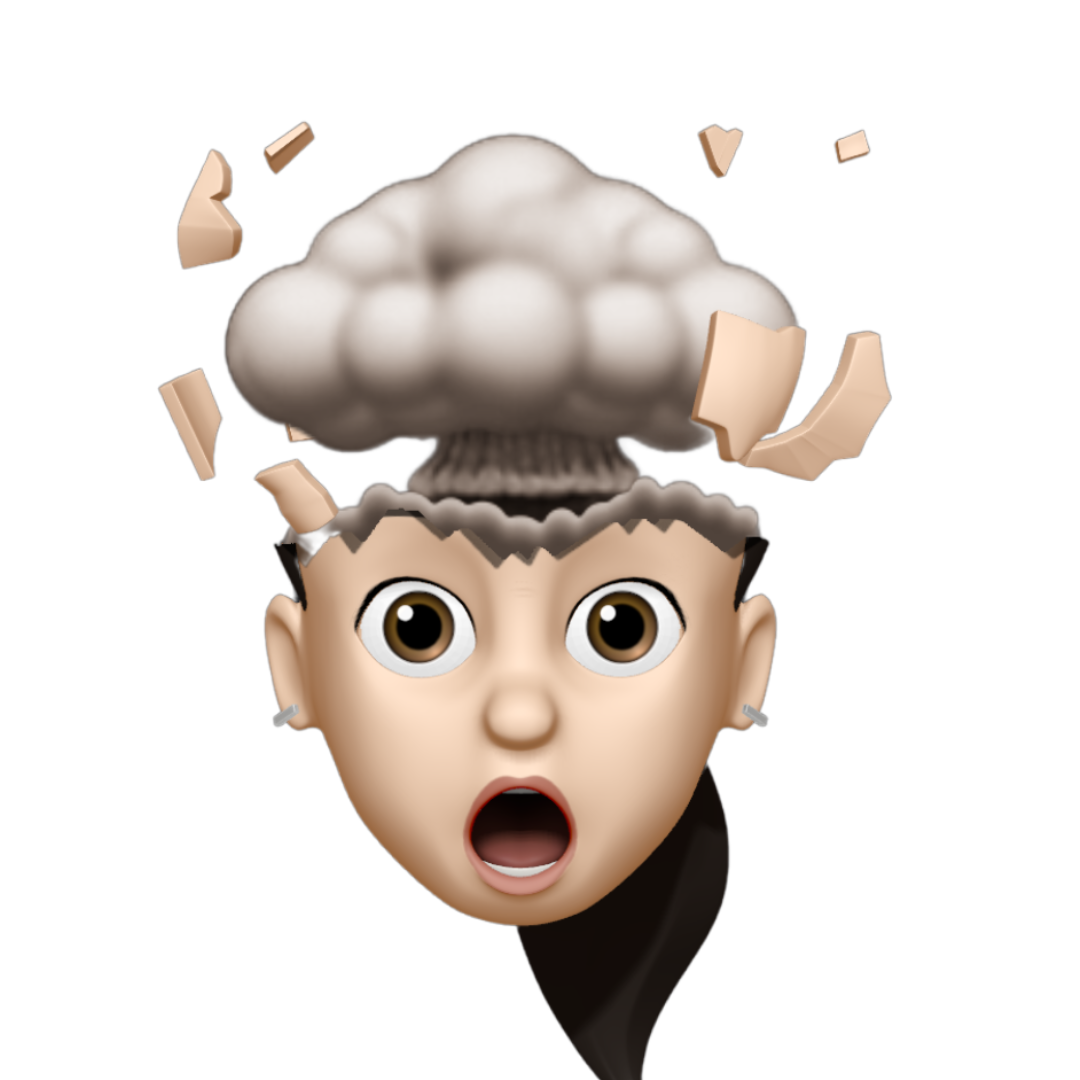
もう、パンチが効きすぎじゃありませんか!?
ド直球に私の心を貫いてきた。笑
そうなのだ。
今ならわかる。私も正しい弔いが終わっていなかったのだ、と・・・。
現在はどうか?と聞かれれば、正直、弔いが終わっているかどうかはわからない。
でも、確実にかつての私とは違う。
これだけはハッキリと言える。
子どもの障害や不登校にまつわる、辛かった・悲しかった思い出は、積極的に手放していきたい。
だって、どれだけ焼き直しをしたって、これからの私たちに役立つことはないのだから。
それと同時に「他人に役立つかも」という考え方も手放そう。
結果的に、誰かの役にたっていることはあるかもしれない。
しかし、私たちの辛く悲しかった経験が「役に立てるといいなぁ」と先に期待するのは、たぶんちょっとこじらせている証拠だ。
まとめ|ここまでお読みくださった皆様へ
傷ついた自分の弔い・・・忘れかけていたことですが、これはいくつになっても必要なことだと思います。
頑張れば頑張るほどに、自分の心が麻痺しがちになり、自分の本心を見失ってしまいがちです。
それに、良くも悪くも心の状態が安定すると、現状維持バイアスが働いてしまう・・・。
つまり、そのままでいることに対して違和感を感じにくくなるという、不健全な状態を招くことになりかねません。
私は今回、ジェーン・スーさんの書籍を通して、自らの心の開放の一歩を踏み出すことができました。
心から出会えてよかったと思う書籍は、『ひとまず上出来』です。
気になるかたはお手に取られてみると、新しい発見があるかもしれません♪

最後までお読みくださりありがとうございました!



