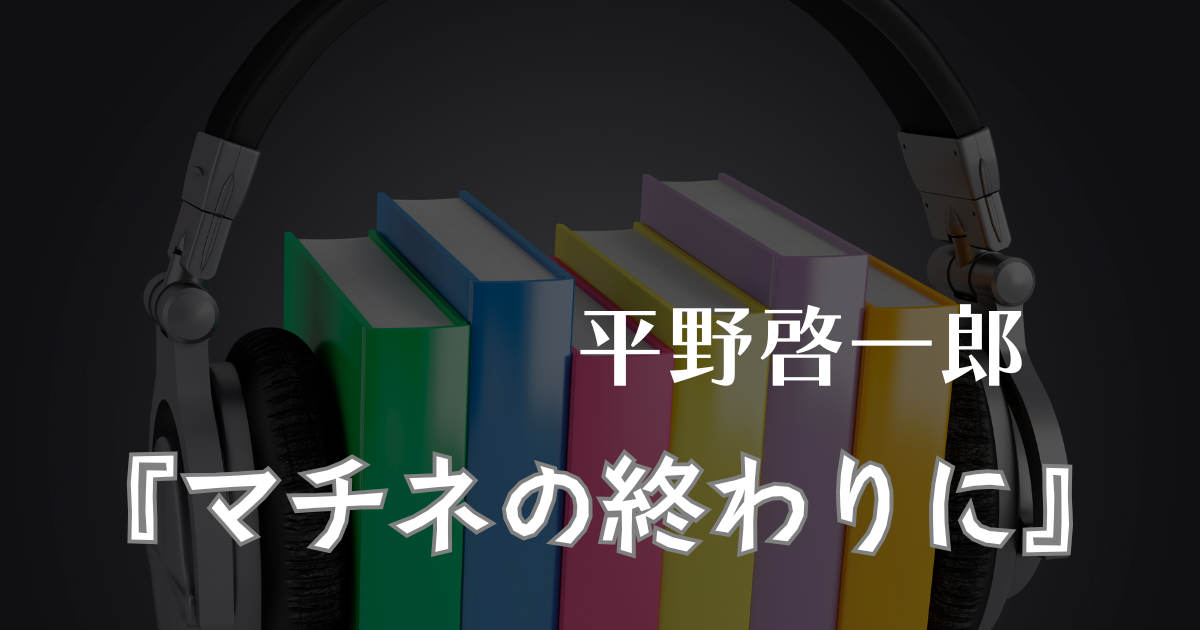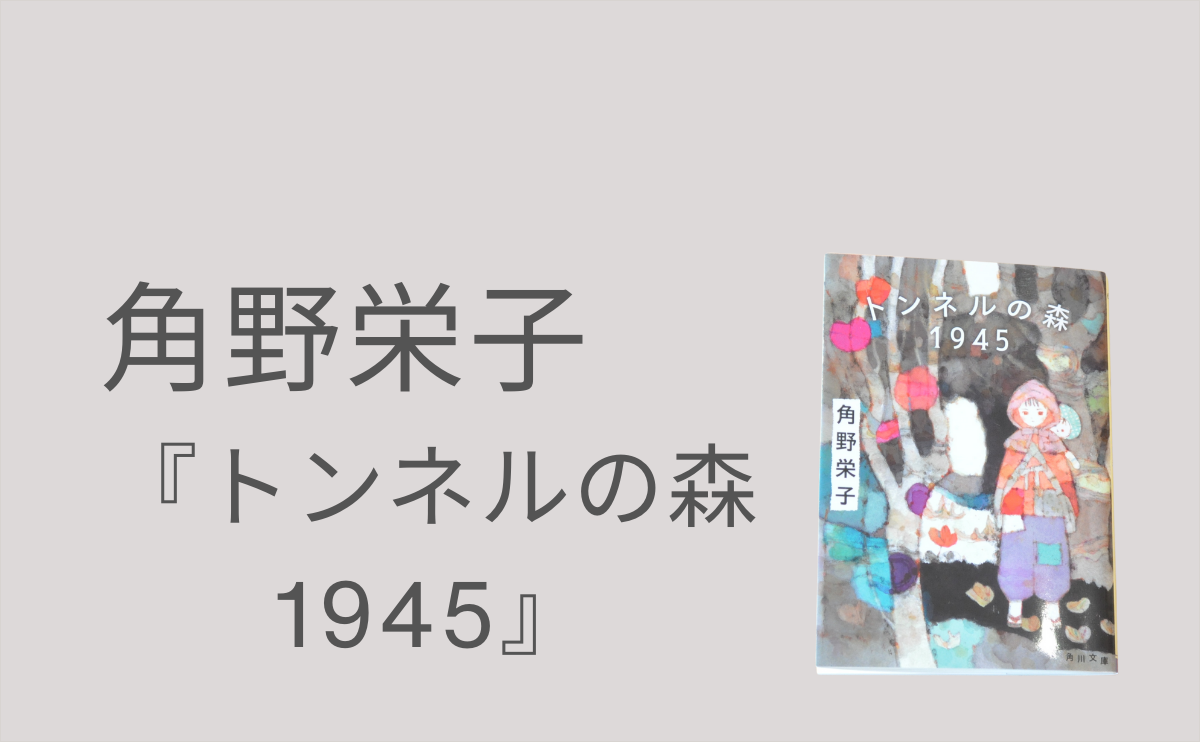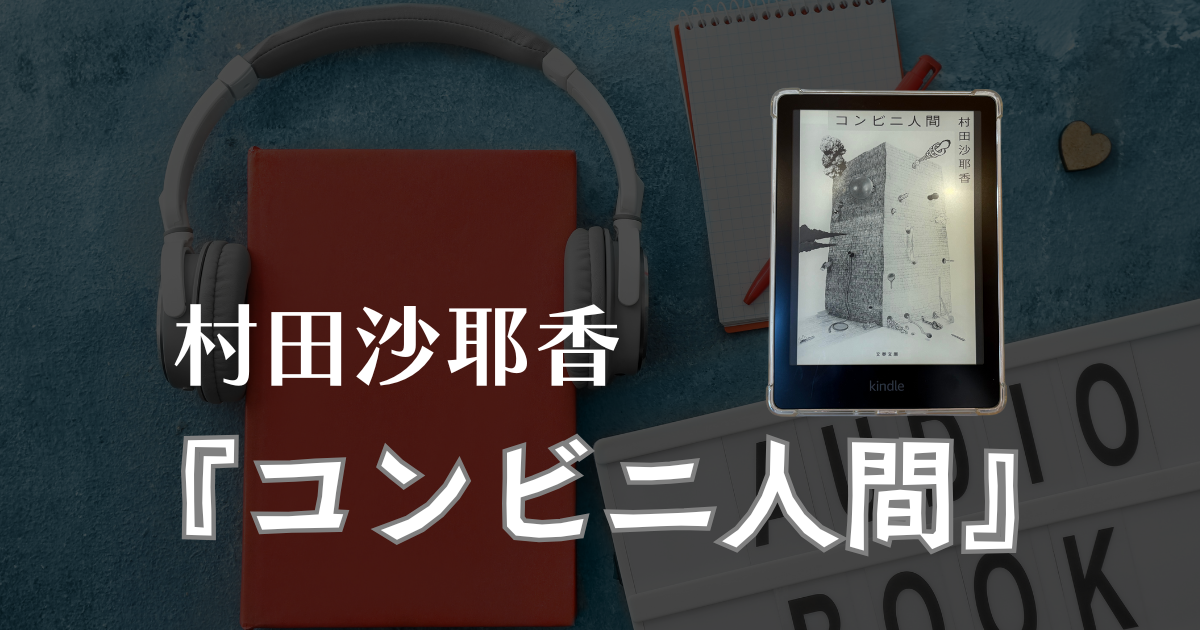久しぶりに心揺さぶられる恋愛小説に出会った。
それが、平野啓一郎さんのご著書『マチネの終わりに』である。
私はAudibleでこちらの書籍に出会っている。
Audibleの魅力と言ったら何と言ってもナレーターによる朗読だと思っているが、羽飼まりさんの声と朗読も、例に漏れず素敵だった。
というわけで、今回は『マチネの終わりに』の読書感想を、背伸びせずに書いてみたいと思う。
Audible版 『マチネの終わりに』 を私なりに簡単に説明してみると
蒔野聡史と小峰洋子というふたりの主人公の恋愛から、『おとな』という言葉について考えさせられた。
惹かれ合うふたりが、すれ違いの連続に見舞われる様子。
それは、読み手としては聴いていてもどかしくなりながらも、ストーリーにどんどん没入していくキッカケになる。
『おとな』の振る舞いを見せてくれた蒔野と洋子の恋愛には、節度があったからこそ、交われる機会をそれぞれに逃してしまうようにも見えた。
しかし、私はこのようにも思う。
相手を気遣うあまり、自分の気持ちを相手に伝えないという選択は、果たして『おとな』の振る舞いなのだろうか?と・・・。
『おとな』の振る舞いを通し、蒔野と洋子が疎遠になってしまう間も、ふたりは決してお互いを忘れることはない。
愛し合っているふたりの気持ちの灯火が、消えることはないのである。
一方で、ふたりは気持に折り合いをつけながら、自分を納得させるように、それぞれの人生の歩みを続けていく。
蒔野も洋子も結婚し、別々の家庭を築き、子どもも生まれる。
それでも時折ふっと脳裏によぎるのは、蒔野は洋子の存在であり、洋子は蒔野の存在なのだ。
順序が前後してしまうのだが、蒔野と洋子が疎遠になってしまう大きなキッカケは、蒔野のマネージャーである三谷早苗の存在である。
蒔野に思いを寄せていた三谷はある出来事をキッカケに、蒔野の携帯電話から洋子に『別れを告げるメール』を送ってしまうのだ。
やがて、三谷の愚行は洋子にバレてしまうこととなるが、洋子は「あなたの幸せを大切にしなさい」という言葉を置き土産にして三谷と別れる。
一方で、蒔野との間にできた子どもを身ごもっていた三谷は、自身の罪悪感を抱えきれなくなり、ついに蒔野に真実を明かしてしまう・・・。
ストーリーに没入している間、私は三谷早苗に対して憤りの気持ちでいっぱいになってしまった。
もし自分が洋子だったら・・・と、考えずにはいられなかったのだ。
しかし、真実を告げられた『おとな』のふたりは、怒り狂うことなく、努めて冷静になろうとしながら、自分の人生に思いを巡らせていた。
故に、このふたりが再会するまでには、時間がかかってしまうのである・・・。
『おとな』とは、どういう人のことを指すのだろう。
蒔野と洋子の振る舞いは、私の目には確かに『おとな』に見えた。
でも、全員の『おとな』たちが、蒔野と洋子のような振る舞い方をできるわけではない。
真逆の反応を示し、蒔野の家庭をぐちゃぐちゃにしようと試みる『おとな』だっているだろう。
そしてまた、そんな人に対して、“あんなにひどいことをしたのだから、それくらい当然の報いだ”とジャッジする『おとな』もきっと少なくはないはずだ。
私は時々、自分のことがわからなくなる。
私は本当に大人なのかしら?と・・・・。
平野恵一論さんの『分人主義』を知る入門書?!
そもそも私が平野啓一郎さんを知ったのは、友人から『分人主義』を教えてもらったことがキッカケだ。
私がまず最初に齧った書籍は『私とは何か――「個人」から「分人」へ』であった。
しかし、理解力の弱い私にとっては“わかるようでわからない・・・”という、なんとも言えない難しさを感じた。 「『分人主義』ってナニ?」と人に聞かれても、言葉に詰まってしまう感覚だ。
そこで、平野啓一郎さんの小説から読んでみることにしたのである。
『マチネの終わりに』を選んだ理由は、いつかどこかで耳にしたことがあるような気がしたから。
それはそうである。なんとこの小説は映画化されていたのだった!(この小説を読むまでは知らなかった)
『おとな』のお手本のような蒔野と洋子の振る舞いであるが、それはあくまでその人たちのほんの一面にすぎない。
そして、『マチネの終わりに』は、子どものように泣きじゃくるとき、家族と一緒に過ごすとき、自分の子どもといる時間、あらゆる時間や人間関係のなかで、私たちはいくつもの「分人」を生きていることが理解できる一冊だった。
職場や学校、家庭でそれぞれの人間関係があり、ソーシャル・メディアのアカウントを持ち、背景の異なる様々な人に触れ、国内外を移動する私たちは、今日、幾つもの「分人」を生きています。
分人主義公式サイトより https://dividualism.k-hirano.com/?id=link-read
現代人が抱えている闇に迫る
現代日本はこんなにも便利で豊かであるはずなのに、社会全体が疲弊しているように見える。
自殺者数が減ることはなく、少子化は進む一方。
「自分自身で精一杯」そんな昨今は、人間関係の希薄さが浮き彫りになっているようだ。
そして私は洋子の言葉をお借りして、「なぜかしら」と問うてみる。
手のひらの中では、いつでもどこでも誰か“繋がれる”のに、なぜかしら・・・。
手のひらの中では、いつでもこどこでも好きな動画や音楽に触れられるのに、なぜかしら・・・。
これはやはり、テクノロジーの進化が人類に莫大な影響を及ぼしているのだと私は思う。
ここでスマホの善悪について議論するつもりは、毛頭ない。
なぜなら、これはスマホに限らずだが、どんなものにも光と影の両面が存在するのだから。
そんな私の心に刺さった一節があったので、ここでご紹介させていただくことにする。
生きることと引き換えに、現代人は際限のないうるささに耐えている。映像も、匂いも味も、ひょっとするとぬくもりのようなものでさえも、何もかもが我先にと五感に殺到して来ては、その存在をかなり立て主張している。ー中略ー誰もが機会だコンピューターだののテンポに巻き込まれて、五感を喧騒に直接揉みしだかれながら、毎日をフーフー言って生きている。痛ましいほど、必死に。
Audible版 『マチネの終わりに』 より
『マチネの終わりに』 読了後の私の変化
平野啓一郎さんの『分人主義』に強い興味を抱いていたので、読了後の私の変化は大きいものとなった。
具体的には、私自身が幾つもの『分人』を生きていることが俯瞰できるようになった。
また、次の本も聴き始めているのだが、『分人主義』を意識して聴くことができている。
ストーリーの中では『分人主義』がさりげなく、しかし存在感を放っていることも感じられて、とてもおもしろい。
小説の効果は絶大である。
【まとめ】ここまでお読みくださったみなさまへ
今回は平野啓一郎さんの『マチネの終わりに』の読書感想を書いてみました。
私にとってこの書籍は、とても哲学的で、幾度となく自分自身を問われる1冊だと感じています。
また、分人主義の入門書として最適な書籍なのではないでしょうか。
ストーリーに没入しやすいため、スムーズに想像となって現れるような美しい景色の描写も、読者が惹きつけられる要因のひとつになっていると思います。

もりー
というわけで、最後までお読みくださりありがとうございました。