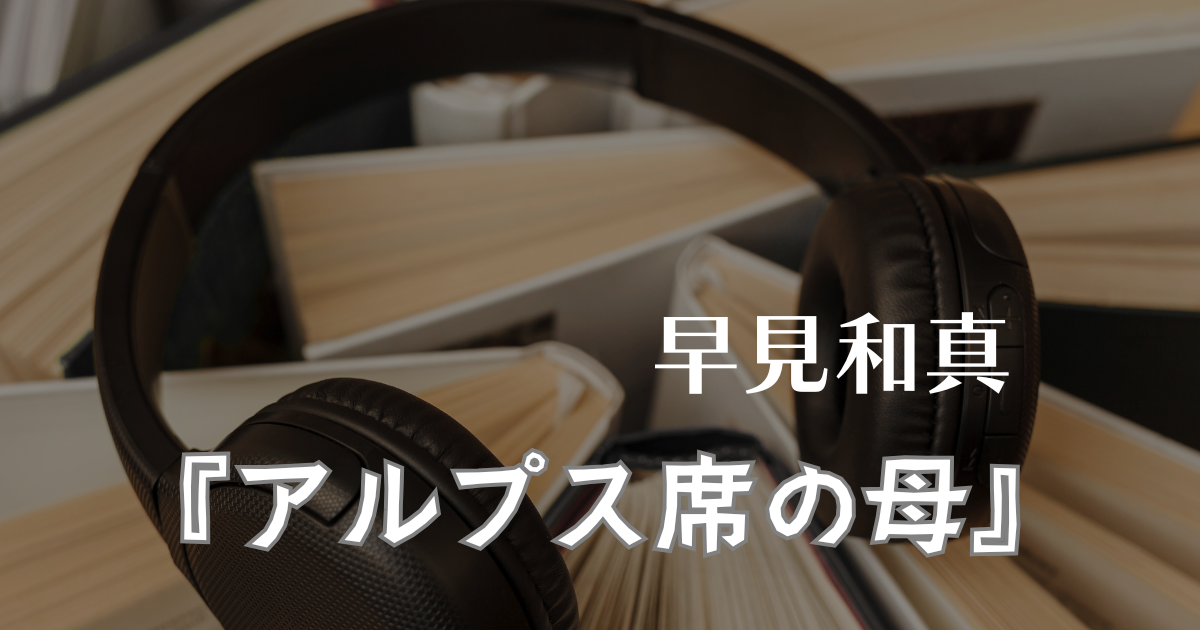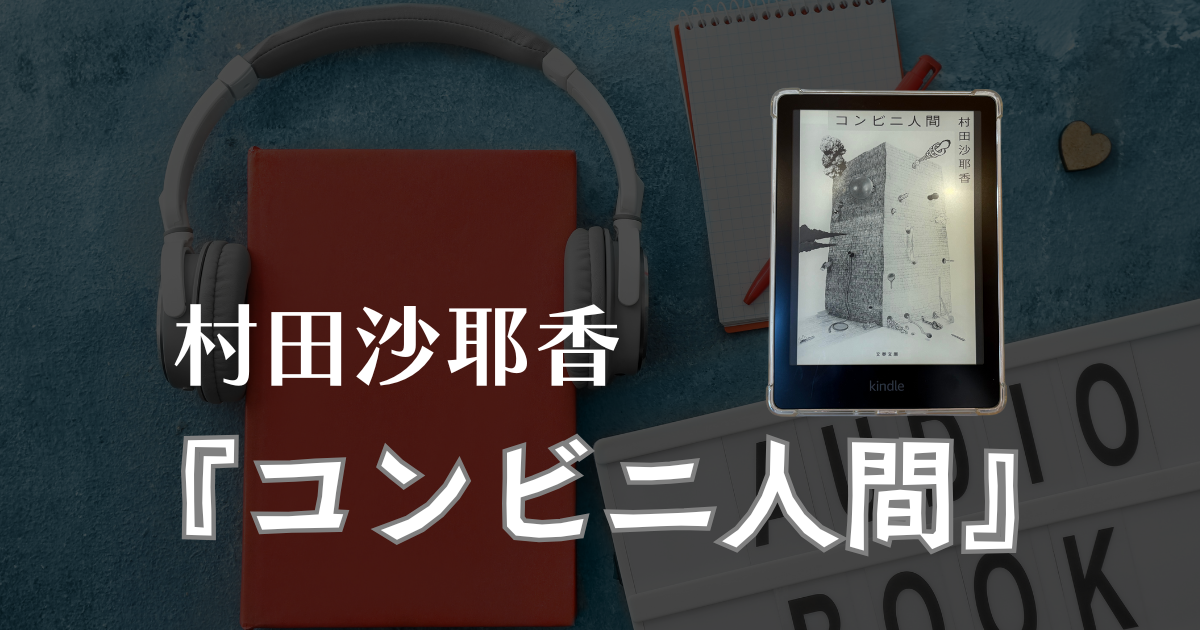私は甲子園どころか、野球自体にかなり疎く、知識はほとんどない。
“野球を知らなくても楽しめるだろうか・・・”という、ほんの少しの不安もありつつ、Audible版『アルプス席の母』を聴いてみることにした。
いざ聴き始めてみると、当初の不安はすぐに吹き飛んだ。
あっというまにストーリーに没入し、終始感情を揺さぶられることとなった。
この書籍は、このような一文からストーリーが幕開けする。
本当は女の子のお母さんになりたかった。
主人公の秋山菜々子は、一人息子の航太郎の母親だ。
菜々子の夫で航太郎の父は事故で亡くなっており、菜々子と航太郎はふたりで暮らしている。
幼い頃から野球が大好きだった航太郎は、父が生きている頃から甲子園に行くことが夢だった。
そんな航太郎と、航太郎の夢を全力で応援し続ける菜々子の物語には、さまざまな感情が紡がれている。
怒り、悲しみ、喜び、葛藤、悔しさ、緊張・・・
言葉では表せないほどの小さな気持ちの揺れが、とても繊細に描かれていることに私は感動した。
著者の早見和真さんのコメントには、このように書かれている。
話を聞かせていただいた元球児のお母さんたちにまず報告したいと思います!
『アルプス席の母』公式サイトより
みなさんの無念を、憤りを、違和感を、ムカつきを、何よりも喜びをめいっぱい乗っけて書きました。
もっと多くの母と息子と、娘と、父にも出会えますように!
早見さんの言葉を見ながら、私はこのように思った。
とても生々しい感情の描写は、早見さんのインタビューと、リアルに現場を経験されたお母さま達の苦労の結晶と言っても過言ではない、と。
『アルプス席の母』を手にとったきっかけ
本屋大賞の受賞が決定する前から、Audibleで紹介されていたこの書籍。
ずっと気になりつつも、先述したように、私はまったく野球などには疎く興味も薄いので、なんとなく触れずにいたのだった。
しかし、本屋大賞を受賞されたカフネを読んだことをキッカケに、その勢いに乗って手にとった次第である。
この件を通して、先入観が邪魔になるこが多いことを改めて痛感した。
とは言え、自分を棚に上げるようでアレなのだが、一冊の本がまた次の本を連れてくるかのように広がっていくことも読書の醍醐味だな、と思うのも本心である。
LGBT+Qの認知が進んだ時代に、男の子のおかあさん・女の子のおかあさんという概念について考える
新しい命を宿したとき、“お腹の子の赤ちゃんの性別”が気になるのは、とても自然なことだと思う。
そして、男の子を望むひと、女の子を望むひと、どちらでもいい!と言うひと、これはほんとうに人それぞれだ。
私はお腹の子が『女の子』と判ったとき、正直ホッとしたことを今でも記憶している。
実は、第一子のときは不妊治療を経ての妊娠だったので、“赤ちゃんの性別なんてどちらだっていい!”と思っていたはずなのに、である。
それはなぜだろう・・・。
男の子は大変そう、という漠然とした不安があったから?
それとも、女の子のお母さんにただ憧れていただけ?
理由はさっぱりわからないが、少なからず出産経験のある女性たちは、そのような気持ちの揺れを経験したことがある人が多いはずである。
現代はLGBT+Qの認知が広がってきたこともあり、男女の性区別に関して、口を出してはいけない傾向が強くなってきた。
しかし、妊娠を望む人たちが、“男の子がほしい”とか、“女の子がほしい”などと望むことは、いけないことなのだろか?
ここで私が不妊治療をしていた頃のお話を、少しだけさせていただくことにする。
不妊治療をしていると、
男の子がいいだの女の子がいいだの、贅沢だ!授かれるだけありがたいと思うべきだ。
という言葉を目にすることが多くあった。
私自身、そのような感情を抱いたことがなかったとは言えない。
今だから言えることだが、このような感情はやっかみ以外の何者でもない。
それぞれの立場で悩みや意見は違って当然であり、立場の違う者同士が、それを互いに押し付けることは不毛な行為なのだと思う。
話を戻すと・・・
この書籍は、『本当は女の子のお母さんになりたかった』から始まっていることは、先述した通りである。
一見、このセリフはとてもさりげなく、なにか特別なインパクトを残すこともないように思える。
しかし、LGBT+Qの認知の広がりと共に、「差別はいけない」というあからさまな道徳的観念を押し付けられるような窮屈さがセットで伴うこの時代に、実はとてもパンチを効かせたワンフレーズなのかもしれない。
そして、どこかでさり気なく流れた「男の子のお母さんでよかったね」というような菜々子のセリフが、今でも私の耳にこびりついている。
『アルプス席の母』と高校球児が教えてくれたこと
「甲子園に行く」という夢を叶えるために、息子を全力で応援しつつ、自分の人生からも目を逸らさずに向き合い続ける菜々子。
野球に人生のすべてをかけていたのは、航太郎だけでなく菜々子もであった。
たった数年の間に、いくつもの人生の岐路に立たされ、そのたびに悩む親子。
それも、自分たちの努力だけでどうにかなることは少なく、そのたびに親子は、それぞれに様々な気持ちを味わうのだ。
そんなジェットコースターのような日々のなかでも、菜々子が自分自身の人生から目を逸らすことはなかった。
喜怒哀楽を素直に味わいながらも、航太郎から子離れしようとする様子が、私にはとても印象的に映った。
そのせいか、航太郎と菜々子の距離感は程よく感じられ、とても心地が良かった。
高校球児の息子に決して依存するのではなく、泣きながらも菜々子は菜々子の人生をしっかりと歩もうとしている姿は、これから子離れが控えている私にとっては、とても滲みた。
【まとめ】ここまでお読みくださったみなさまへ
早見和真さんの『アルプス席の母』は、野球好きのかたはもちろんのこと、野球にあまり興味がないかたも、『人生』という観点から楽しめる一冊です。
Audible版では、河井春香さんの朗読による大阪弁も聴けるので、より臨場感を楽しめるはずです。
多様性だの、☓☓ハラスメントだの、差別偏見はいけないだのと、道徳的観点がまるでマニュアルのようになり、逆に世の中がピリついているように感じられる昨今。
だからこそ、野球に全力を注ぐ男の子と、男の子のお母さん、そしてかれらを取り巻く物語は、とても痛快に響くのかもしれません。

もりー
というわけで、最後までお読みくださりありがとうございました。