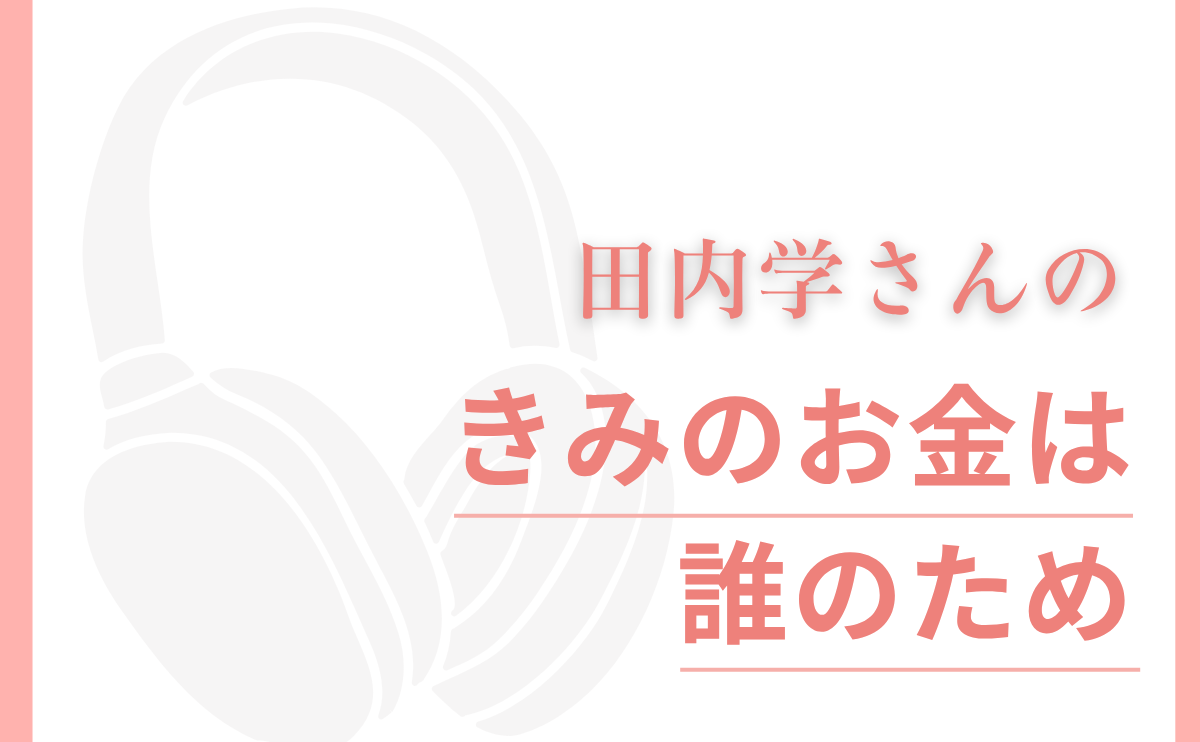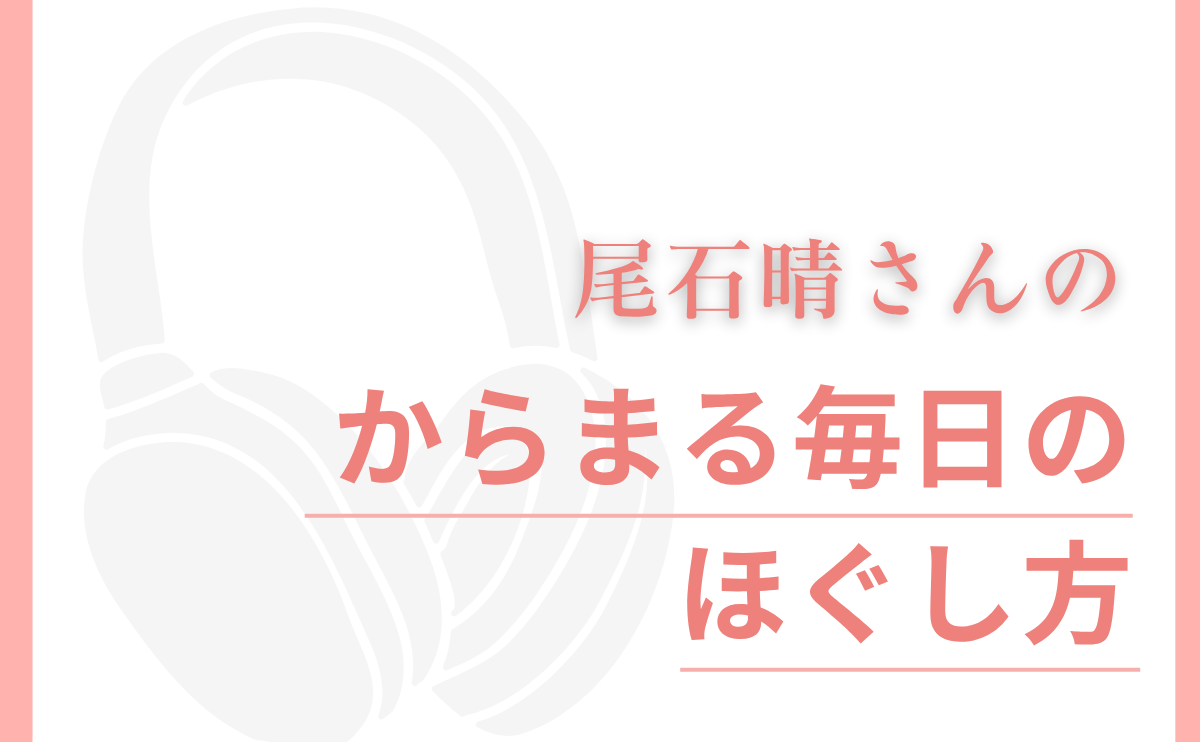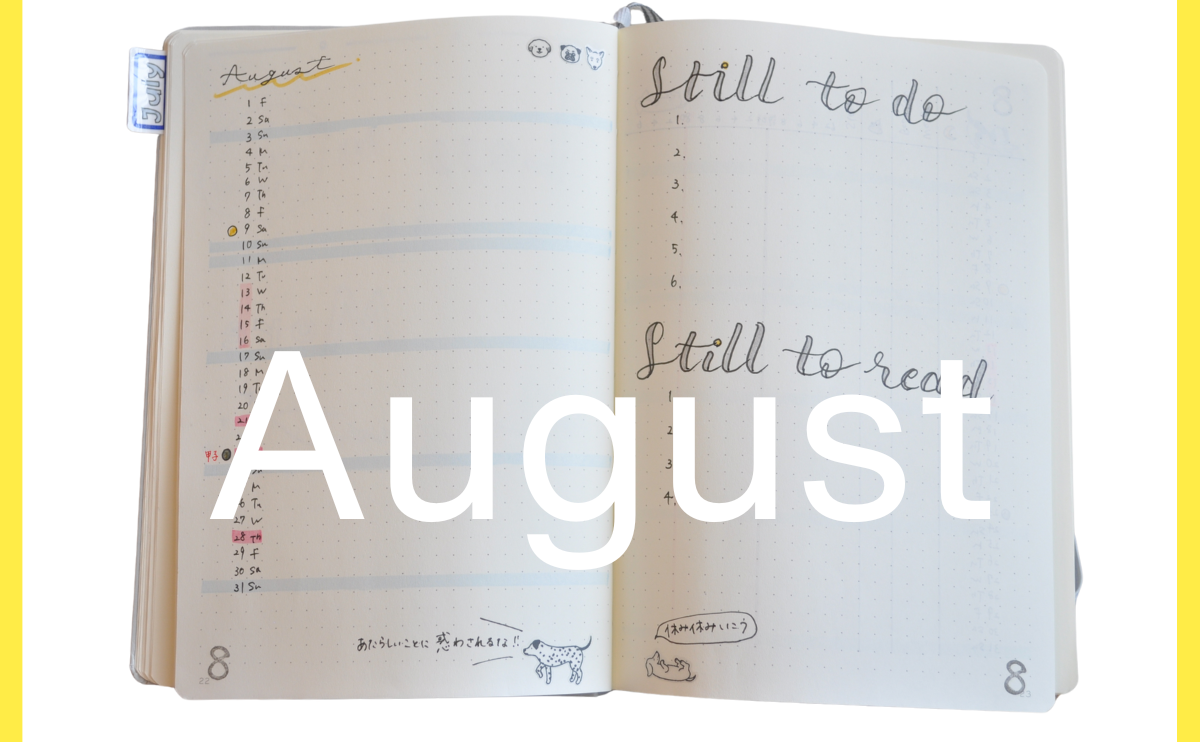『きみのお金は誰のため』に触れてみたきっかけ
Audible内で気になる本を探していたとき、ふと目についたのがこの本でした。
サムネイル画像には『日本中で大反響!15万部早くも突破!!』と書かれていてるではありませんか!
これは読んでみるしかないな・・・という気持ちになり、聴き始めた次第です。
読後の変化|お金の流れが水のように見えるようになった
「ボス」と呼ばれる男性が、お金の流れを水にたとえて説明する場面があります。
読み進めていくうちに、自然と、お金の“イメージ”が湧いてきました。
具体的には、「あ、お財布からお金が流れていったな~」とか「お財布にお金が流れこんできたな~」という感じです。
これまでの私は、お金を支払うときに「お金が減ってしまった」と感じていました。
通帳の額面を見たときも同様で、「増えた・減った」と数字だけを見て理解していました。
それが、流れるというイメージに変化したのです。
世間ではよく「お金は天下の回りもの」と言われたりしますが、まさにその通りなのだと思います。
お金は「貯める」よりも「巡らせる」
お金はついつい貯めたくなるし、貯まると嬉しくなるもの。
一方で、減れば不安になり、将来に対する焦りが生まれがちです。
たしかに、個人の視点ではそう感じるのは自然なことかもしれません。
しかし、社会全体で見てみると・・・必ずしも「貯める=正解」ではないのか?と気づきました。
お金は「稼ぐより「使う」ほうが難しい、とよく耳にしますが、それは真理なのだと思います。
労働力の低下は今後の日本の大きな課題?!
どんなに大金持ちだったとしても、労働力がなければ、それを使うことすらできません。
- お店で働くひとがいない
- 農業や酪農を営むひとがいない
- 土木建築系の職人さんがいない
- 清掃業者で働く人がいない
- 林業をやる人がいない
- 工場で働く人がいない
思いつくままに挙げてみましたが、想像しただけでも社会の機能は成り立たなくなってしまうと感じます。
お店は閉まり、花壇は草で覆われ、街路樹には虫がつき、ゴミは集積所からあふれ・・・。
想像しただけでゾッとします。
このままいくと、日本の未来は本当にこうなってしまうかもしれません。
食料が買えなくなれば、田舎の農家さんに分けてもらうしかないかもしれない。
あるいは、自分の庭に畑を耕すことになるかもしれません。
でも、お米は?小麦粉は?
素人が一朝一夕に作れないものもたくさんあるのです。
日本の労働力の低下は本当に深刻だと思わずにはいられません。
「金を払ってやってんだからやって当たり前」といった態度は、言語道断ですね・・・。
「手触り」が薄れている日本の現代社会
本書の中で語られていた「社会に手触りがある」という言葉がとても印象に残りました。
かつては、誰かの顔が見える距離で働き、商売をし、感謝の言葉を交わすことが当たり前でした。
しかし今は、スマホひとつで買い物ができ、誰とも会話を交わさずに完結してしまいます。
結果的に、「商品がどのようにして作られ、どれだけの人の労働が関わっているのか」を想像するのが難しくなりました。
その影響と言ってよいのかはわかりませんが、価格中心の見方で判断するようになってしまった気がします。
知らず知らずのうちに、「人々の労働が社会とどうつながっているか」を感じにくくなっているのかもしれません。
それでも、お金の流れや仕事の意味を見直すことで、「人の働き」と「社会のつながり」を再び感じ直すことができる。
こんな気付きを、この書籍から得ることができました。
まとめ|ここまでお読みくださった皆様へ
私は『きみのお金は誰のため』に触れたことで、お金の見え方が変わりました。
お金=水のように流れるものとイメージできるようになり、減った増えたの数字以上に、流れや人々のつながりに目が向くようになったり。
また、お金の価値は“労働”があってこそ成立するということも、強く実感しました。
社会の中で誰かが働いてくれているからこそ、自分の生活が成り立っている。
そう気づくだけでも日常の見え方が変わります。
そしてここで、長い間専業主婦として生きてきた私が少し安心したワンフレーズをご紹介させてください。
お金をもらう労働だけでなく、家事や育児なども同じく労働である。
人々の労働の価値は『お金を稼ぐことだけではない』ということを感じることができる一文だと思います。
お金、社会、そして“働く”ということについて、じっくり考えるキッカケを与えてくれる一冊です。
少しでも気になったかたは、ぜひAudibleで聴いてみてください。

もりー
最後までお読みくださり、ありがとうございました!