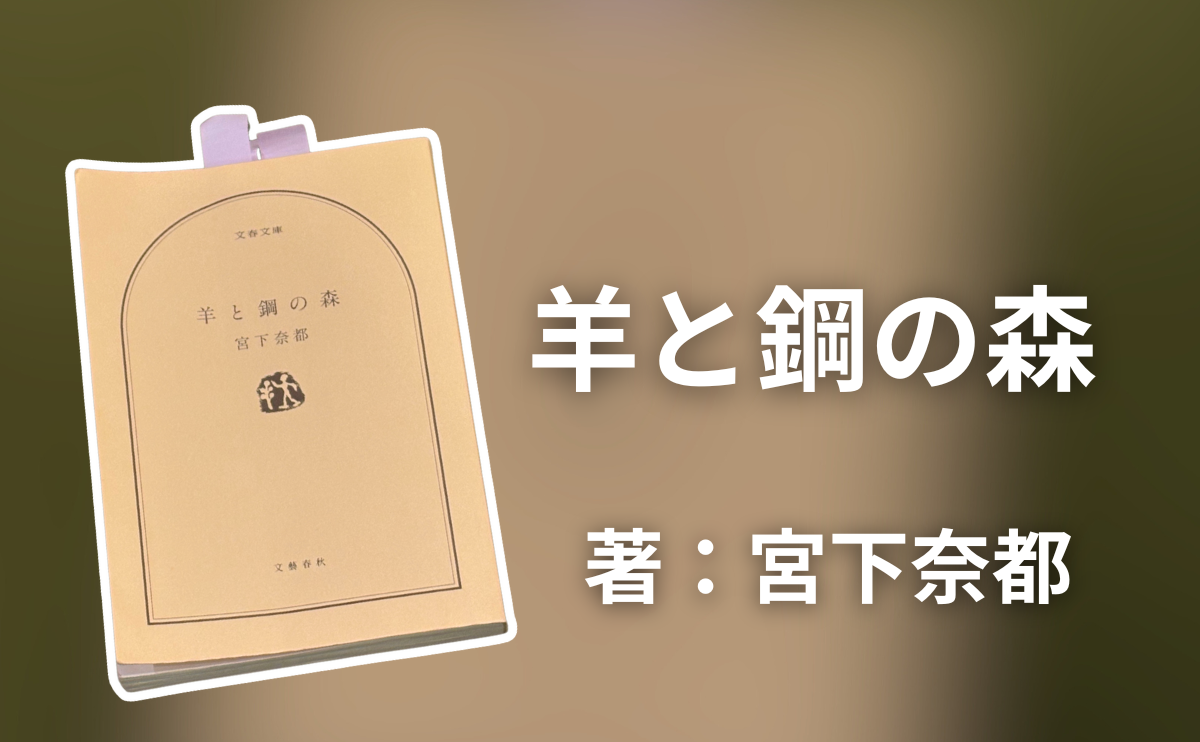傷は、癒やすもの。
傷は、癒えるもの。
いつの間にか、そんな前提を抱えたまま生きてきた気がします。
宮地尚子さんの『傷を愛せるか』は、トラウマや心の傷を「克服する方法」を示す本ではありません。
臨床の現場に立つ専門医でありながら、ひとりの人として、驚くほど率直な言葉で綴られています。
この記事では、本書を読んで心に残った問いと、深く沁み込んできた言葉をご紹介していきます。
『傷を愛せるか』の第一印象|書店で吸い寄せられるように出会った1冊
書店で吸い寄せられるように出会った、宮地尚子さんの『傷を愛せるか』。
白を基調としたカバーと、雪のような写真に惹かれ、思わず手に取りました。
帯の下の方には、太めのゴシック体でこのように書かれています。
トラウマ研究の第一人者による深く染みとおるエッセイ
『傷を愛せるか』 帯より
この一文を読み、宮地尚子さんという方は“トラウマ研究の第一人者なのだ”ということを初めて知りました。
本書は、臨床心理学の知見を背景にしながらも、専門書というよりは、静かな語り口のエッセイとして綴られています。
そして、購入の決め手となったのは、帯に書かれているこの一文です。
傷を抱えて生きる全ての人に
本書帯より
この本を強く握った私は迷わずレジに向かいました。
「傷を癒さなければならない」という前提への違和感
この作品タイトルは、私たちに強烈な問いを投げかけてくれているような気がしました。
私自身、「無理に傷を癒やさなくてもいい」と思ってきました。
けれど、“愛せるか”という問いを向けられたのは、これが初めてでした。
ここで「愛せるか」と問われると、思わず立ち止まってしまいます。
そして同時に、もし愛することができたなら、それはとても強い在り方なのかもしれないと、ぼんやり思うのです。
ASD姉妹と暮らす私の心に、深く沁みた一節
人からアドバイスや助言を受けたとき、それをすんなり受け入れられないことは珍しくありません。
善意でかけてくれている言葉だとわかっているからこそ、受け取れない自分を責めてしまう・・・そんな経験は、多くの人に思い当たるところがあるのではないでしょうか。
ASD姉妹を育てている私は、これまで嫌というほど、こうした場面を経験してきました。
そんな私が、とても深く「これだ・・・!」と感じた文章があります。
溺れそうなときに、たくさんのことを言われても耳に入らない。身体を少しずつ水に慣らし、恐怖をやわらげていくしかない。
溺れそうな気持ち。必死で手足をばたつかせないと、沈んでいきそうな感覚。息苦しくて、なにがなんでも水面上に顔を上げてしまいたくなる気持ち。すくんで縮こまる身体。何かにしがみつきたくなる衝動。上手に泳げるようになったら、忘れてしまうであろうその感じを、できればずっと覚えていたい。
本書より
この文章は、机上の空論ではなく、実体験をもとに紡がれた著者の言葉です。
臨床の現場で医師として、母親として、そして一人の人として葛藤を抱えてきたからこそ、この表現が生まれたのだと思います。
だからこそ私は、この言葉が心の奥にまで沁み込んできたのだと感じました。
傷を愛せるか?|傷の見え方が変わり、向き合い方が変わる
本書の223ページから、「傷を愛せるか」というテーマが正面から語られます。
この章を読みながら、私はあらためて「傷」について考えるきっかけをもらいました。
そして同時に、「傷」という言葉から、具体的なイメージがほとんど浮かばなかったことに、少し驚いたのです。
宮地尚子さんは医師としての立場から、実に多様な視点で「傷」を捉え、さまざまな傷のあり方を具体的に示していきます。
その中で、次の言葉が綴られています。
傷は痛い。そのままでも痛いし、さわれれると、もっと痛い。
傷を愛することはむずかしい。傷は醜い。傷はみじめである。直視できなくてもいい。
本書より
傷の痛みや醜さが、ここまで率直に言葉にされているからこそ、私はこの感覚をごまかさずに認めてもいいのだと思えました。
むしろ、「直視できなくてもいい」と許されたことで、不思議と、傷を直視できるような感覚が生まれたのです。
さらに、文章はこのように続きます。
傷がそこにあることを認め、受け入れ、傷のまわりをそっとなぞること。身体全体をいたわること。ひきつれや瘢痕を抱え、包むこと。さらなる傷を負わないよう、手当てをし、好奇の目からは隠し、それでも恥じないこと。傷とともにその後を生きつづけること。
本書より
ここで語られている「傷との向き合い方」は、とても具体的で、わかりやすいものでした。
それは医師としての視点によるものなのだと思います。
しかしそれは決して事務的ではなく、傷を負った人の身体と心を、まっすぐに見つめている言葉だと感じました。
まとめ
『傷を愛せるか』は、私にとって「傷」というものを、あらためて深く考えるきっかけになった一冊でした。
外傷であれば、傷がふさがり、痛みが引けば「治癒した」と判断できます。
けれど,心の傷はとても見えにくく、癒えたのかどうかさえ、自分でもわからないことがあります。
向き合うことに疲れて、いつの間にか見て見ないふりをしてしまうこともあると思います。
けれど、治癒しきれていない傷は、知らず知らずのうちに不平不満となり、心の奥に蓄積していくのかもしれません。
このタイトルに少しでも心が動いた方は、ぜひお手に取って読まれてみてください。
きっと、自分の中の「傷」との距離が、少し変わるはずです。

もりー
最後までお読みくださりありがとうございました。